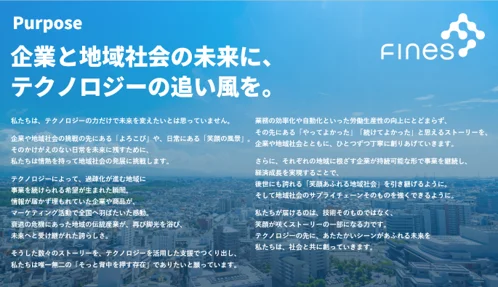
動画マーケティングを核とし、DX支援を手掛ける株式会社ファインズ(東京都港区、代表取締役社長:三輪 幸将)は2025年9月26日付で、今後の事業計画および成長戦略を策定したと発表した。中小企業を主要顧客と位置づけ、AIやデータ活用を軸としたソリューション拡充を図る構えである。
本稿では、同社の新戦略のポイント、背景、課題と展望を整理しつつ、「動画DX企業の進化の行方」を探る。
既存ポートフォリオと顧客基盤──縦横に広がる事業の足がかり
ファインズは現在、VideoクラウドとDXコンサルティングを2本柱とし、動画活用・分析とマーケティング支援を核に事業展開してきた。これまでに12,000社を超える企業に導入実績を持つという。
顧客層の中心は従業員100名以下の中小企業であり、この層こそが日本企業全体の98%以上を占める現実を背景に、同社は「DX後れ」状態にある中小企業を主戦場と見定めている。
この構図を前提に、新戦略の骨格は「動画×DX×AI」という3軸統合型ソリューションへの変革であり、従来の“動画ツール提供中心”から“包括的成長支援パートナー”への進化を志向している。
新戦略の3本柱:受注拡大・人材確保・生産性向上
発表された計画では、中小企業が直面する三大課題—「受注拡大」「人材確保」「生産性向上」—をターゲットに据え、以下のような施策を打つと明示されている。
① 受注拡大支援
既存のVideoクラウドを軸としつつ、マーケティング・営業支援ツールを拡張。顧客の新規販路開拓や広告最適化支援を強め、動画からの流入を受注につなげる“エンドツーエンド支援”を模索する。
② 人材確保支援
採用難・人件費高騰という構造課題を受け、採用DX化・企業ブランディング支援・定着率改善支援を強化。中小企業の“人の壁”を技術とノウハウでブレークする狙いだ。
③ 生産性向上支援
まだアナログ依存の強い業務プロセスに対し、AI・自動化・業務設計を導入支援。動画だけにとどまらず、バックオフィスや営業支援まで範囲を広げ、企業競争力を底上げする施策が目立つ。
加えて、AIエージェントの自社開発研究を積極的に打ち出しており、サービスの中核にAI要素を統合していく戦略も示されている。
収益モデルをフロー型からストック型へ
これまで同社の売上構造は、案件ごとの“都度発注型(フロー型)”が中心であった。しかし策定された戦略では、ストック型収益基盤の構築を明確に標榜している。
具体的には、Videoクラウド・DXソリューションを組み合わせた複数サービス提供による継続課金モデル化や、契約更新・アップセル・サブスクリプション化を通じて、安定した収益構造への転換を目指す方針だ。
組織・制度改革:外部知見導入と経営体制強化
戦略実行のため、ファインズは外部人材の登用や経営組織強化にも言及している。CXOクラスや戦略コンサルタントの招聘、経営戦略高度化への投資といった施策を通じ、外部視点の取り込みと実行力の底上げを図る意図があるようだ。
また、パーパス・バリューを起点とした組織運営を深化させるため、OKR・1on1・エンゲージメントサーベイ導入や人事制度刷新も進める計画である。
戦略実現へのハードル
この成長戦略を軌道に乗せるには、以下の点が試金石となるだろう。
・サービス横断統合の整合性:動画・DX・AIを一体化して提供するには、技術と組織の強い連携が不可欠
・中小企業向けの価格競争力維持:高機能化と低コスト両立の難しさ
・実行速度とリソース調整:新戦略投資を急がなければ、競合に先行を許すリスク新戦略投資を急がなければ、競合に先行を許すリスク
・定量的成果の可視化:顧客に対する投資対効果(ROI)を示す指標整備の重要性
動画DX企業から「包括的DXパートナー」への転換
ファインズが今回示した成長戦略は、動画DX企業からさらに一歩踏み込んで「中小企業の経営課題を横断的に支援する包括的パートナー」への進化を志向するものと評価できる。
動画という訴求力ある入り口を軸に、DX・AIを融合させた戦略は、顧客企業にとっての“体験価値”を引き上げる可能性を秘めている。
一方で、その変革を実現するには、戦略を動かす現場の実行力やシステム整備、契約設計、顧客評価指標の整備など多くのチャレンジが重なる。
これからファインズが、新戦略をどのように具現化し、中小企業支援市場でのポジションをどう拡大していくか──その“脚さばき”が、業界注目のポイントとなりそうだ。
※本稿はPR記事です。









